【高糖質食、糖質制限食、高脂肪食、ケトン食、それぞれの効果の違いを答えられますか?】
『スポーツ栄養学:科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』寺田新・著 Vol.149
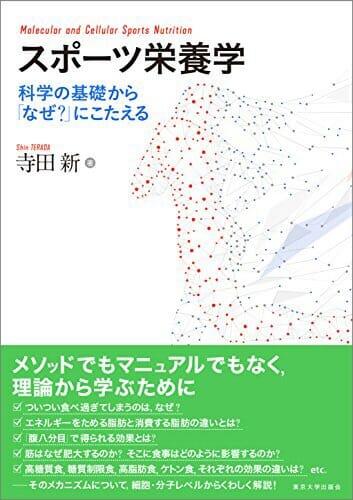
本日ご紹介するのは、『スポーツ栄養学 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』。
手にした第一印象は、「大学で学ぶ栄養士の教科書みたい」。
しかし、「つい食べ過ぎてしまうのは、なぜ?」「エネルギーをためる脂肪と消費する脂肪の違いとは?」「筋はなぜ肥大するのか?そこに食事はどのように影響するのか?」「高糖質食、糖質制限食、高脂肪食、ケトン食、それぞれの効果の違いは?」「脂肪、油、脂、脂質の違いは?」など帯の気になるキャッチコピーに惹かれ、カバーも綺麗だったこともあって購入を決めました。
各章の末には膨大な参考文献が記してあり、それらの知見をまとめて一冊の本で読むことができると考えれば時間効もよく感じます。
最近は食事法のノウハウ本をかいつまむことが多く、栄養に関する知識はまだまだ不足していると感じていたため、基本と理論から学びたいとも考えていました。 小難しそうに見えた本ですが僕の手にした本で、発売から半年で「第3刷」になっていることから、売れているのでしょう。
<より長時間の運動では、ケトン体を生成し、それを利用できるようになることで、メリットが得られる可能性がある。たとえば、超長時間運動時において、エネルギー補給の回数を減らせる。>
6月10日(日)に開催された、第7回飛騨高山100キロウルトラマラソンでトップの選手は丸腰で、給水所でも水ぐらいしか補給せずに走り続け、いくらゴールタイムが8時間、9時間で速いといってもエネルギー補給が少なすぎるように見えました。日ごろの食生活から気をつけ、脂肪がエネルギーとしてどんどん使われる体、ケトン体質を作り上げているのでしょうか。トップウルトラランナーの食生活が気になりました。
食事や栄養に関する知識が弱い部分だと感じている方は、ぜひ勉強してみてください。
▼ここから
最近の研究では、たんぱく質の摂取量をむしろ減らしたほうが、ある部分においては好ましい結果をもたらす。
エネルギー摂取量を毎日30%程度減らすことで寿命が延びる可能性がある。
エネルギー糖質制限は、内臓脂肪量を減らし、糖尿病などの生活習慣病の予防に効果的である。
高齢者においては、たんぱく質量摂取の減少は、加齢性の骨格筋委縮であるサルコペニアの進行を助長することに加えて、血中のアルプミン濃度の減少も引き起こす。
トランス脂肪酸の摂取量がエネルギーあたり2%増えると、心疾患の発症リスクが20%増加すると推定されている。ただし、日本人の平均的な摂取量は、エネルギー摂取量の1%未満であり大きな影響はない。
トランス脂肪酸による影響は、その摂取量だけではなく、それ以外に摂取している脂肪酸、特に不飽和脂肪酸(その中でもリノール酸)によっても変わってくる。
トランス脂肪酸は、反芻動物の胃においても生成されるため、牛肉や牛乳を摂取する人はトランス脂肪酸を摂取してることになる。
より長時間の運動では、ケトン体を生成し、それを利用できるようになることで、メリットが得られる可能性がある。たとえば、超長時間運動時において、エネルギー補給の回数を減らせる。
糖質に加えて牛乳を同時に摂取することで、消化管ホルモンおよびインスリンの分泌が刺激され、筋グリコーゲンの回復が促進される可能性が高い。
▲ここまで
【高糖質食、糖質制限食、高脂肪食、ケトン食、それぞれの効果の違いを答えられますか?】
『スポーツ栄養学:科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』寺田新・著 Vol.149